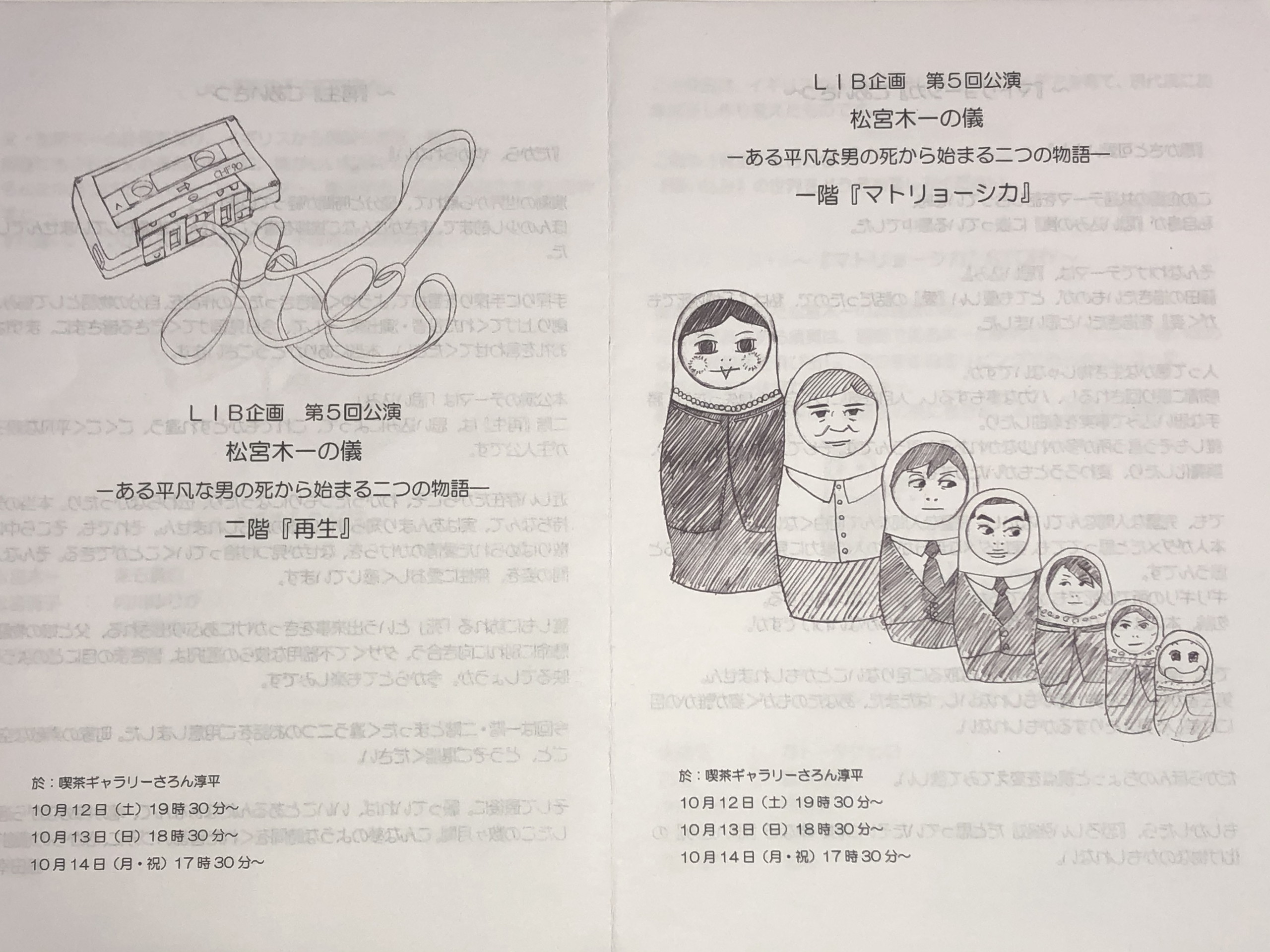前書き
2019年10月14日(月)
この日は『マトリョーシカ』、『再生』という二つの演劇を鑑賞してきた。
人生において、演劇を見た経験はほとんどない。おそらく、両手で数えられる程度である。
(誰も勘違いしないと思うが、2進数で数えて1023回程度、という意味ではない)
小説や映画にはほんの少しばかり親しんできたように思う。しかし、演劇に関しては微かな興味を抱きつつも、自発的に鑑賞したことはこれまで一度もなかった。かつて演劇が盛んな京都の街で学生として過ごし、しかも不真面目ながら美学・芸術学を専攻していたにもかかわらず、である。
そんな私だが、ここ2年ほどの間に何回か観劇の機会を得た。いずれも、あることがきっかけで知り合った俳優、ガトータケヒロ(@7_Gateau_3)の活躍を見るためである。
10年以上も前の自分の不真面目さに今更ながら幾ばくかの反省を示しつつも、演劇の楽しさを少し理解してきた私は、今回もふらふらと観に行った次第である。
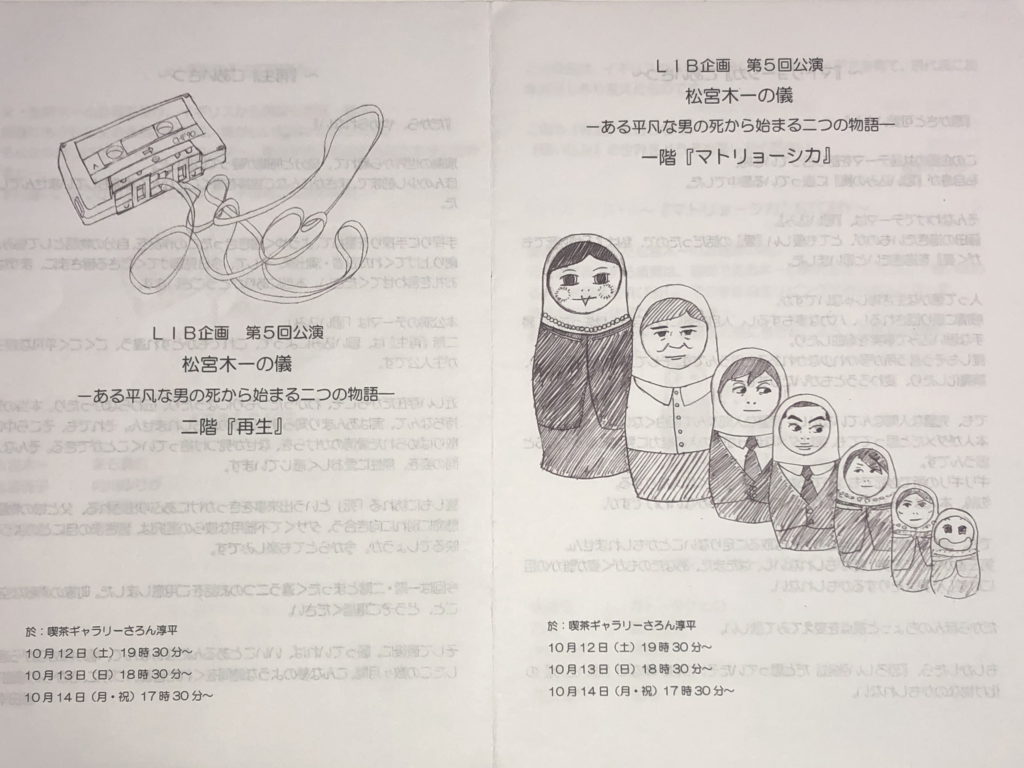
(当日のフライヤー。イラストはガトータケヒロによるもの)
基本情報
タイトル:松宮木一の儀―ある平凡な男の死から始まる二つの物語―
場所:喫茶ギャラリーさろん淳平

公演期間:2019年10月13日~10月14日
制作:LIB企画
作・演出・構成:皆都いづみ、藤田幸
主演:
『マトリョーシカ』
佐藤巧(ガトータケヒロ)
詩央(香川由依)
庄野哲夫(河野充)
御園(上野有佳子)
須賀優作(福丸)
『再生』
松宮木一(末石貴広)
松宮雛子(内川ゆりか)
悦子(丸田章世)
庄野哲夫(河野充)
あらすじ
『マトリョーシカ』
剣道部の顧問だった松宮木一が病死した。かつて剣道部の部員であった須賀優作は、松宮の葬儀の日、自分は悔い改めると言い残してその場を飛び出してしまう。
優作の様子を不審に思った元部員の佐藤巧と庄野哲夫は、彼の後を追いかける。そして彼らは、優作が自宅のリビングで死亡しているのを発見した。
優作が納豆アレルギーを持っていたことに気づいた巧。もしかして優作は、自分が通夜振る舞いで差し出した納豆が原因で死亡したのではないかと焦る。
そこに、優作の妻が戻ってくる。巧と哲夫は優作の死亡時刻をずらして自分たちのアリバイを作るべく、行動を開始する――。
『再生』
松宮木一の訃報を受けて、急遽イギリスから帰国した娘の雛子。葬儀の途中、父親の遺品を整理していると、父親には不似合いなものを発見する。
雛子の進む道を頑なに認めようとはしなかった木一。彼が録音したと思われる一本のテープを再生していくと、そこには自分の知らないもうひとりの木一がいた。
感想
全体
演劇というと、ホールでの上演を思い浮かべがちである。かくいう私も、過去の観劇経験はすべてホールであり、それ以外の会場で見たことがない。
今回の講演場所は、町家のカフェ。普段は机が置いてあるのであろう少し細長い空間を中心に、両端にある入り口を使って俳優が出入りするという構成になっている。
暗幕などはない。本来、本作は夜の講演のみであった。そのため、暗幕を使わなくても暗転を表現できたのだろう。
私が見たのは、諸事情にて急遽追加された昼の講演。しかし、暗転がなくてもそれほど違和感は覚えなかった。
約2時間の講演のうち、前半が『マトリョーシカ』、後半が『再生』である。ふたつの話は松宮木一という人物の死を通じた連作となっており、前半に出てきた登場人物や話題などが後半になって触れられる様子や、もしくはその逆が見られる。
『マトリョーシカ』は1階、『再生』は2階で上演される。観客は先に1階で鑑賞したあと、休憩時間に2階へ移動し、次の劇を見るという流れである。
舞台が狭いと大道具や小道具などが使い辛いのはもちろんのこと、音楽や光の演出、さらには俳優の動きまで自然と限定される。そのため、観客の視界に入る情報もまた限定されがちである。早い段階で視界の情報は固定されてしまい、それ以上の想像を許さないだろう。
『マトリョーシカ』が終わった段階で、既に1階の舞台は『マトリョーシカ』のものだ。同じ階でふたつの話を上演していたならば、後半の舞台は前半の舞台情報に引きずられてしまう可能性がある。
たとえそれぞれが異なる内容であったとしても……否、違う内容であるからこそ、その印象は拭いにくい。なればこそ、舞台そのものを変えることで視界に映る情報をフォーマットし直す。少なくとも、その効果は出ていたのではないか。実際にそんな意図があったかどうかはわからないが、面白い工夫だったように感じた。
ただし、それは形式上の話である。できれば1階と2階に分けたことが、話の内容にも深く影響してくると、より面白かったように思う。
舞台が狭いということは、それだけ観客と俳優との距離が近いということでもある。
どちらの作品も非常に印象的だったのが、俳優の表情が隅々まで見えるという点。ホールのような舞台では、演じている俳優の声は聞こえても、その表情まではっきりと確認するのは難しい。それが狭い舞台になると、どのような顔で演じているのかがよくわかる。
動きについても同様だ。距離が遠いと俳優の動きの全体はわかるかもしれないが、どこか客席から俯瞰しているような感覚が抜けない。
距離が近いと、その分だけ俳優の動きは間近でダイナミックに迫ってくる。実際、今回の劇における観客と俳優との距離は最短で1mも離れておらず、視界に作品世界が地続きで広がっているような印象を与えてきた。
特に印象に残ったのは、『マトリョーシカ』の作中でガトータケヒロ演じる佐藤巧が汗をかくシーン。登場した彼の顔や服は、汗でびっしょりと濡れていたのがよくわかった。こうした姿は、ホールの上ではあまり目立たなかったかもしれない。狭い舞台であったからこそ、映える演出だったといえる。
マトリョーシカ
『マトリョーシカ』では、いくつもの登場人物の勘違いが交錯していく様子を、喜劇的に、かつ悲劇的に描いている。
物語は、剣道部の顧問である松宮木一の葬式に参列していた男、須賀優作の死から始まる。
剣道部の元部員であった須賀優作。彼は納豆アレルギーを抱えていた。同じ元部員であった佐藤巧と庄野哲夫は、須賀の死が自分たちのふるまった納豆のせいであると思い込んでいる。
死亡時刻を操作して自分たちのアリバイを作ろうとした巧たち。しかし、優作の家に詩央という女性が来たことで、巧たちは窮地に立たされる。
優作の妻であるらしい詩央。死体が見つかるのは時間の問題であり、巧と哲夫への疑いは避けられそうにない。
どうにかして優作の死体を隠しながら、死亡時刻を操作する必要がある。そう考えた哲夫は、死亡時刻をごまかすためドライアイスの確保に奔走。その間に巧は詩央の目から須賀の死体を隠すべく、得意の話術で彼女の気を逸らし始める――。
もちろん、既にいくつかの勘違いが生じている。まず、優作が死亡した原因は、巧が出した納豆のせいではない。納豆アレルギーによる症状は何時間も後になってから発生するためだ。優作の死亡時刻は、どう考えても納豆アレルギーによる症状の発症時期とは合わないのである。
また、詩央は優作の妻ではなく、愛人である。彼女が平然と須賀の家にやってきたため(もしくは既に家にいた?)、巧と哲夫は彼女が優作の妻だと思い込んでしまったわけだ。
そして詩央もまた、ある勘違いをしている。彼女は別れ話を切り出した優作の頭部を冷凍うどんで殴り、そのまま気絶した優作を放置していた。優作に付着した血の量から、詩央は自分が優作を殺したのだと自覚していたのである。
しかし、うどんは密度が小さいため、冷凍しても撲殺できるほどの強さはない。つまり優作の死因は、詩央に殴られたことでもない。
互いが互いの勘違いや嘘を利用しながらも、自分の勘違いには気づいていない。須賀という男の死を中心に、勘違いにまつわる喜劇が繰り広げられる。そこにミステリタッチなネタばらしをエッセンスに加えているのが、本作の魅力である。
……表面的にはそうなのだが、須賀の死因を考えると、本作はどこか気持ち悪さを残すものとなる。
巧と詩央が胸中にそれぞれの思惑を宿しながらやりとりをしているなかで、1人の女性がやってくる。彼女の名前は御園。優作の「本当の」妻である。御園は妊娠悪阻のため実家に滞在しており、所用で家に戻ってきたあと、再び実家へ行くつもりをしていた。
巧と詩央、そして優作の様子を見た御園。彼女は優作が巧と詩央を招き入れ、ふたりを残して眠りこけているのだと勘違いした。そして、残された巧と詩央に対して詫びながら、もしお腹が空いているならと、優作に作っておいたという冷やし中華を差し出す。
物語のラストでは哲夫の口から、冷やし中華が納豆アレルギーの人に対してアナフィラキシーを引き起こすことがあると伝えられる。
詳細については少し記憶が曖昧だが、優作は御園が作った冷やし中華を食べていたようだ。だとするならば、優作の死因は、御園が作った冷やし中華によるアナフィラキシーの可能性が高い。
納豆アレルギーを引き起こす原因は、納豆のネバネバと同じ成分を持つPGA(ポリガンマグルタミン酸)である。
PGAは冷やし中華のスープのほか、健康飲料やスポーツ飲料、さらには石けんなどにも含まれる。それぞれのPGA含有量は定かではないが、事実ならば普段の生活にはある程度注意しておく必要があるだろう。
だとすると、優作を死に至らしめたのは御園の冷やし中華ということになる……その事実を知った巧と詩央が顔を見合わせながら、物語は幕を閉じる。
優作の妻である御園が、彼のアレルギーのことを知らなかったとは考えにくい。優作の生活について、普段から気を遣っていたのは間違いないだろう。
冷やし中華によるアナフィラキシーショックが原因だとするなら、意図的にそれを狙って殺せたのは御園だけである。こうしたオチが最後に明かされることで、本作はただの喜劇ではない、別の一面を見せることとなる。
ここで、御園の殺意におけるifを設定したとして、殺意がなかったというのはまずあり得ない。先に述べたように、御園は優作の妻であり、彼の納豆アレルギーに対してアナフィラキシーを起こす食べ物を知らないとは考えにくいからである。結婚生活にあたり、少なくとも優作からこうした食べ物や日用品がダメだと聞かされているはずである。
つまり、御園には殺意があるということになる。ただ……そうするとミステリ的には少し疑問が残る。
遅かれ早かれ、優作の死は知れ渡ることとなる。納豆アレルギーに対して冷やし中華がアナフィラキシーを引き起こすということは、世間的な認知度が低いとはいえ(少なくとも私も作中の人物たちも知らなかった)、専門家が死因を確かめればすぐに分かることだろう。
ならば、冷やし中華を出した御園は、自分がそれを作ったことを隠そうとするのが自然である。
にもかかわらず、御園が巧や詩央に対して冷やし中華を出すのは、自分で「私が犯人です」と言っているようなものだ。この点は、少し矛盾があるように思う。
もちろん、何らかの理由によって自分が犯人であると気づかせることが目的なら、その行動もわからなくはない。その辺の説明が不足しているように感じたのはちょっと惜しい気がした。
しかし、そうした点を抜きにしても、巧と詩央の掛け合いは面白く、見ていて引きつけられるものがある。
結婚を間近に控えている巧は、自分が加害者として疑われることはなんとしても避けなければならない。葬儀屋という、どこか後ろ暗い部分を残す仕事に就きながらも、巧はようやくつかみ取れそうな幸せを必死で守ろうとする。
切羽詰まった状況に対する焦りの色と、勘違いによる喜劇的な雰囲気とのギャップ。こうした二面性が、ガトータケヒロの演技によって見事に表現されていたといえる。
一方、優作に対して殺意に近い感情を抱いていた詩央。自分が殺人を犯したと思い込んでいる詩央の様子は、表面上は普通に見えるのに、少しずつその病的な様子が顔をのぞかせるのが印象的だ。
詩央を演じる香川由依はガトーよりずっと小柄であるにもかかわらず、狭い舞台の上を彼とともに縦横無尽に動き回る。その動きはダイナミックで、決して彼の動きに気圧されていない。香川もまた、人を殺したという異常な精神状態と、愛憎入り乱れた感情をうまく演じていたように見えた。
ところで、タイトルの『マトリョーシカ』は何を意味していたのだろうか。
マトリョーシカとは、ロシアの伝統的な民芸品として親しまれている人形だ。人形は上下に分割されており、中にはさらに小さなマトリョーシカ人形が入っている。たいてい、数体の人形が入っている入れ子構造になっているのが特徴である。
タイトルの意味を単純に推測するなら、自分が殺したかも知れないという「思い込み」の人形を開けてみると、そこには別のものが隠されていた、ということを表しているのだろう。
ただ、パンフレットを見ると、本作はイギリスの古いミステリー小説にアイデアを得て作成したとある。私はミステリに疎いのでどの作品にアイデアを得たのかはわからないが、もしかするとタイトルの意味は別のところにあるのかもしれない。
再生
『再生』は、松宮木一の娘・雛子が、亡くなった父親の遺品であるテープレコーダーを再生することで、父親に対する思い込みに少しずつ気がつき、やがて父親の優しさに触れていく物語である。
本作では、雛子や友人の悦子が登場する葬式後の様子と、生前の松宮木一の独白が平行して描かれる。交わらないはずのふたつの時間軸はゆっくりと近づいていき、やがて交差したその瞬間に、互いの思い込みや誤解が解けるようになっている。
本作で印象的な点は、やはり松宮木一のキャラクターだろう。
頑固一徹という言葉が相応しい性格の木一。彼は雛子のことを大切に育ててきたが、やがて夢を追いかけようとする雛子と仲違いしてしまう。家を飛び出した雛子とは、それきり二度と会えずにこの世を去ってしまった。
再生されたテープの節々からは、決して木一が頑固なだけの人物ではなかったことがわかる。自分のキャラクターに合わないことをしてでも娘を理解しようとする様子からは、まさに周囲の思い込みとは異なる姿が立ち上がる。
物静かな雰囲気と頑固さ、そして娘を大切に思うあまりに見せるギャップが、末石貴広の演技によって上手く表現されていたように感じる。派手な動きがない分だけキャラクターの演じ分けは難しかったのではないだろうかと、素人ながらに思ってしまう。
なお、『再生』にはふたつの物語の発端となった松宮木一本人が登場していることから、『マトリョーシカ』の回答編のようなものを想像していたのだが、そこまで踏み込んだ内容のものではなかった。
ふたつの作品のつながりといえば、松宮木一の死を除けば、『マトリョーシカ』に登場していた庄野哲夫が『再生』でも少し登場する程度である。個人的には『再生』まで通しで見ることによって、『マトリョーシカ』だけでは知り得なかった事実が明かされる、という展開を期待していたのだが……。
家族ものとしては少し盛り上がりに欠ける展開ではあったが、それでも最後のシーンで木一と雛子があり得ないはずの相互理解を深めていくところは、妙に引きつけられてしまった。それもまた、スクリーンを隔てずに直接見ることができる「舞台」のなせる技なのかもしれない。
ミステリ仕立てで描かれていた『マトリョーシカ』に対して、家族ものとしての優しい雰囲気に満ちた『再生』。作品の方向は異なっていても、連作としてはバランスの取れた構成になっていたのではないだろうか。